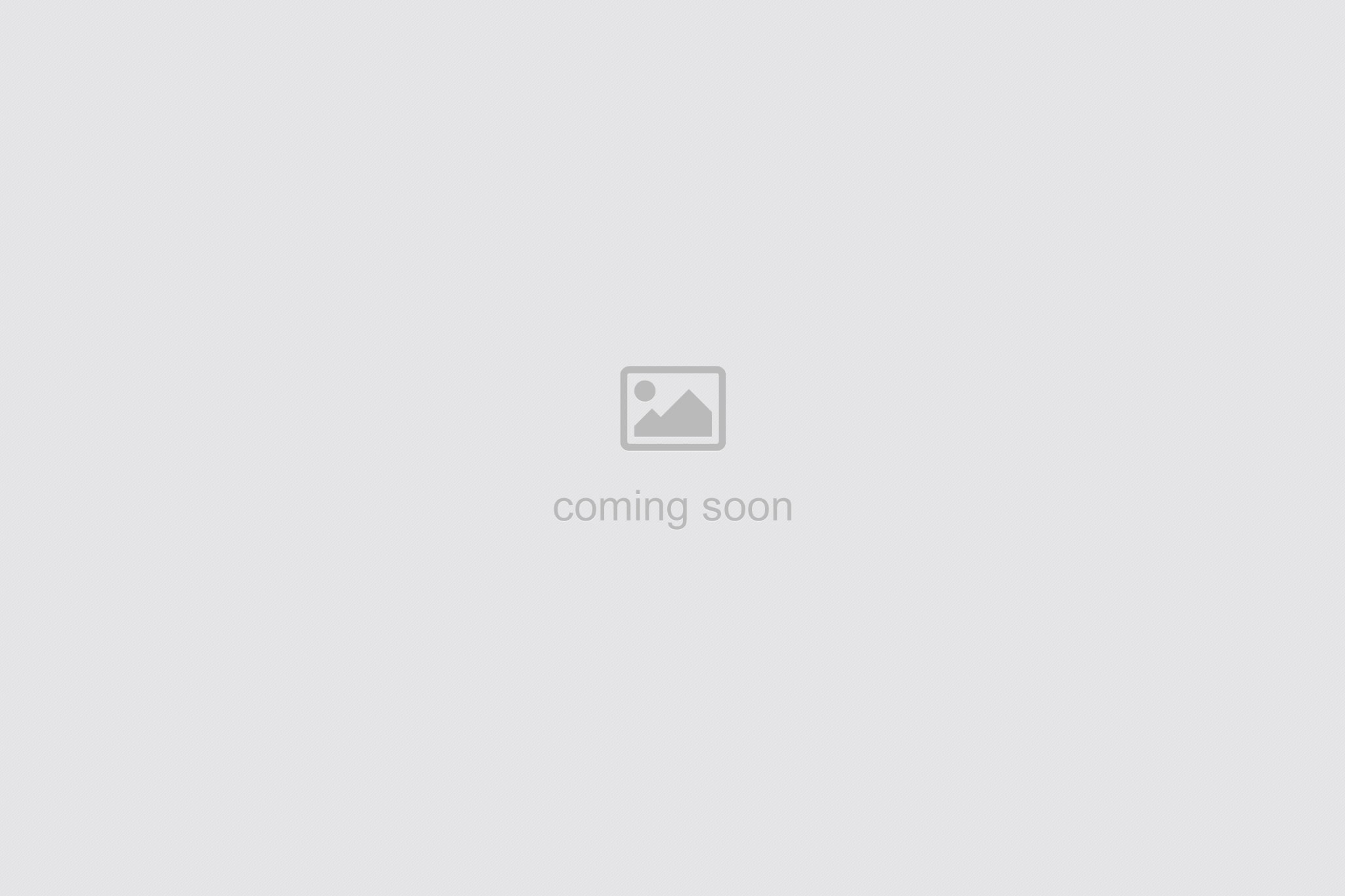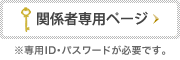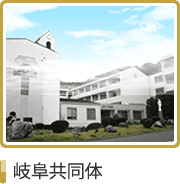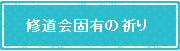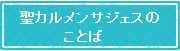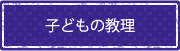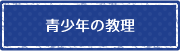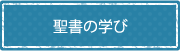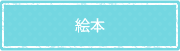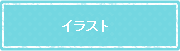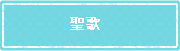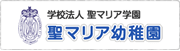聖書の学び資料
キリスト教の始まり
マルコによる福音 15 33-47節
イエス様をはじめその弟子たちはユダヤ教徒でした。キリスト教が始まったのはイエス様の死と復活の後、教会の誕生は聖霊降臨によってです。聖霊降臨によって弟子たちが宣教を始めたことで、周囲の人々から初めて「キリスト者」と呼ばれるようになったのでした。
今日は、そのイエス様の死と復活の場面を読みました。これこそキリスト教の中心です。しかし、この死と復活の場面を4つの福音書で見比べると、それぞれ描き方が全く異なります。弟子たちにとってイエス様の死の体験、復活の体験はそれぞれ違っていたのです。死と復活については、事実よりもその人個人の体験が重要で、イエス様が実際にどのように亡くなり、どのように復活したのかは問題ではありません。私たちがそれらを通して何を体験し、何を感じるのかが大切です。現代の私たちには、この出来事を知る材料は聖書しかありません。この聖書を通して、私たちはどのような体験をすることができるのでしょうか。聖書を通して死と復活の場面を思い描き、その場に自分もいるようにイメージして祈るという黙想の仕方があります。話の登場人物として、そのイメージの中で実際に自分が動き、話し、触り、見るのです。この祈りを通して、きっと何か体験することができるでしょう。イエス様の死の場面は、劇的な表現が用いられています。大声を出して息を引き取られると、神殿の垂れ幕が真っ二つに裂けてしまいました。これは実際の出来事というより、マルコの用いた象徴的な描写であると考えられています。イエス様の身体を象徴する神殿が崩壊したと解釈する場合もありますが、神殿の垂れ幕とは、神殿の中で私たちの立つ場所と神様のおられる聖所とを隔てていた幕、つまり聖所に入ることができないようにと設けられた幕です。それが避けたということは、聖所に入ることができるようになった、つまりイエス様の死によって、神に至る道が開けたと解釈することもできます。私たちと神様とを隔てているものは何でしょう?そして、イエス様によってその隔たりが取り除かれていますか。また印象的な場面として、百人隊長の姿があげられます。百人隊長とはローマの軍隊の隊長です。つまりユダヤ人にしてみれば異邦人。ユダヤ教の社会では蔑まれていた存在である百人隊長が「本当にこの人は神の子だった」と、信仰告白しています。また、「百人隊長がイエスの方を向いて、側に立っていた」という記述も、特に印象的です。神様に心を向けているのです。「回心」という言葉は、「悔い改める」というより、「心を神に向ける」ことを意味しています。神に心を向けているこの百人隊長こそ、私たちの回心の模範のような気がします。そして、その時に出てくる言葉が信仰告白であったことも、大きな意味があるように思います。人は、回心した時に本当の信仰告白ができるのではないでしょうか。私たちはイエス様に出会った喜び、イエス様を知った時の喜びをもっているはずです。その喜びを人々の前で告白する勇気がありますか?復活の後、イエス様は弟子たちに「全世界に言ってすべてのつくられたものに福音を宣べ伝えなさい」と言われました。これは私たちに対しても言われている言葉です。宣教とは信仰告白であり、宣教はキリスト者の使命です。洗礼を受けたからには、宣教する義務があります。むしろ、もしイエス様に出会ったことを本当に喜んでいるなら、その喜びを人々に伝えたくなるはずなのです。
今日、もう一つ考えたいことは、「待つ」ということです。イエス様が亡くなって復活するまでに、聖土曜日という沈黙の丸一日があります。亡くなった金曜日のうちに、弟子たちはイエス様を墓に収め、日曜日の朝まで待ち続けたのです。安息日には外を出歩くことも遺体に薬を塗ることも許されず、ただ待ち続けなければなりませんでした。この弟子たちや婦人たちの思いを味わってみてください。そして、自分が何かを待ったことのある経験を思い出してみてください。「待つ」ということは、この次に何かがあるのです。喜ばしいことを期待して待つこともありますし、嫌なことをドキドキしながら待つこともあります。待つ時の気分はどのようですか。そして、イエス様不在のまま日曜日を待つ弟子たちは、どのような気持ちだったでしょうか。それから迎えた日曜日に、イエス様は復活して戻ってきました。その時の喜びはどれほどだったでしょう。その喜びが大きければ大きいほど、復活の喜びを人々に伝えたくて仕方がなくなるのです。宣教はむしろ、自然な心の動きです。自然に内から湧き上がる喜びを、人々に伝えていきたいと思います。